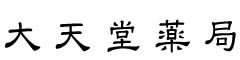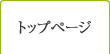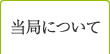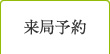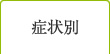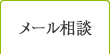2011年05月09日
★「O111」ってどんな細菌?★
「今問題となっている『O111』はどんな細菌?」
「どうすれば予防できるの?」
気になりますよね。
先日の日経新聞にQ&Aがありましたので
参考にまとめてみました。
Q1 細菌0111とは?
A1 体内に入ると腸管に出血をもたらす大腸菌の一種で
1996年に堺市などで大きな被害をもたらした0157と同じ仲間だ。
「o」というタイプの抗原を持つ大腸菌で「111]は発見された順番だ。
Q2 主な生息場所は?
A2 牛などの腸管がすみかで、家畜には害をもたらさない。
生肉を食べるなどして人の体内に入ると、食中毒になることもある。
食中毒は細菌が増えやすい夏にかけて増加するが、
0111など腸管出血性の大腸菌は感染力が強く、夏以外でも被害の報告が多い。
感染から1週間後に発症することも少なくない。
Q3 被害をもたらす仕組みは?
A3 菌がベロ毒素という成分を出し、腸管で出血が起こる。
毒素は腎臓にも作用し、腎機能が失われてしまうケースもある。
溶血性尿毒症症候群を起こし、血液透析が必要になる。
脳症になり意識障害など起こすと、危険な状態に陥る。
Q4 どんな人が発症しやすいのか?
A4 大人は感染しても症状が見られないケースも多いが、
子供や高齢者は発症リスクが高い。
便を介して発症する可能性もある。
Q5 予防法は?
A5 生肉を避け、十分加熱する。
肉の中心部を摂氏75度以上で1分間以上加熱すれば菌は死滅する。
肉を焼く際の取り箸と食べる箸を使い分けることも大切。
調理器具は消毒し、生肉を触った手やトイレの後はしっかりてあらいする。
Q6 ほかの食中毒への対処法は?
A6 鶏や牛などの腸管にいるカンピロバクターやサルモネラ、
豚や鹿などのE型肝炎ウイルスなども同様で、食材を十分に加熱することが重要だ。
肉が新鮮でも菌は動物の腸管にもともといるので注意が必要だ。
(日経新聞参照)
十分加熱すれば大丈夫です。
適切に対応しましょう。

にほんブログ村
「どうすれば予防できるの?」
気になりますよね。
先日の日経新聞にQ&Aがありましたので
参考にまとめてみました。
Q1 細菌0111とは?
A1 体内に入ると腸管に出血をもたらす大腸菌の一種で
1996年に堺市などで大きな被害をもたらした0157と同じ仲間だ。
「o」というタイプの抗原を持つ大腸菌で「111]は発見された順番だ。
Q2 主な生息場所は?
A2 牛などの腸管がすみかで、家畜には害をもたらさない。
生肉を食べるなどして人の体内に入ると、食中毒になることもある。
食中毒は細菌が増えやすい夏にかけて増加するが、
0111など腸管出血性の大腸菌は感染力が強く、夏以外でも被害の報告が多い。
感染から1週間後に発症することも少なくない。
Q3 被害をもたらす仕組みは?
A3 菌がベロ毒素という成分を出し、腸管で出血が起こる。
毒素は腎臓にも作用し、腎機能が失われてしまうケースもある。
溶血性尿毒症症候群を起こし、血液透析が必要になる。
脳症になり意識障害など起こすと、危険な状態に陥る。
Q4 どんな人が発症しやすいのか?
A4 大人は感染しても症状が見られないケースも多いが、
子供や高齢者は発症リスクが高い。
便を介して発症する可能性もある。
Q5 予防法は?
A5 生肉を避け、十分加熱する。
肉の中心部を摂氏75度以上で1分間以上加熱すれば菌は死滅する。
肉を焼く際の取り箸と食べる箸を使い分けることも大切。
調理器具は消毒し、生肉を触った手やトイレの後はしっかりてあらいする。
Q6 ほかの食中毒への対処法は?
A6 鶏や牛などの腸管にいるカンピロバクターやサルモネラ、
豚や鹿などのE型肝炎ウイルスなども同様で、食材を十分に加熱することが重要だ。
肉が新鮮でも菌は動物の腸管にもともといるので注意が必要だ。
(日経新聞参照)
十分加熱すれば大丈夫です。
適切に対応しましょう。
にほんブログ村
Posted by 望月 伸洋 at 07:00│Comments(0)
│健康