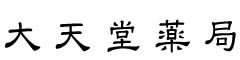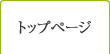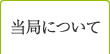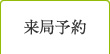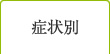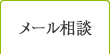2010年10月16日
生還者に心のケア必要 PTSD、うつ病の恐れも…
チリの鉱山落盤事故から無事33人が救出されました。
これから、経験した彼らにしかわからない辛い現実が待っています
しっかりしたサポートも必要ですが、彼ら自身が治れるかどうかだと思います。
命ある限り明るく楽しいことがあるのも事実
現実を受け入れ、焦らず前向きに乗り越えてほしいと祈ります
(以下読売新聞より。)
チリの鉱山落盤事故で、過酷な閉鎖空間に2か月以上閉じこめられていた33人。
救出された作業員たちは元気そうに救助隊員らと抱擁したが、
心身にさまざまな異常が起きることが懸念されるため、
専門家は中長期を見すえた治療とケアの必要性を強調している。
作業員の健康問題で、今後も手当てが必要なのが「心の傷」だ。
恐怖場面が繰り返しよみがえるフラッシュバックや不眠が生じるPTSD(心的外傷後ストレス障害)、
うつ病などを発病する恐れがあるからだ。
防衛医大防衛医学研究センターの高橋祥友教授(精神医学)は
「突然に長期間、隔絶された空間で死の危険にさらされた作業員たちの受けたストレス
は計り知れない。アルコールや薬物依存に陥る可能性もある」と話す。
高橋教授によると、少なくとも1年間は、心身の健康を定期的にチェックする必要があり、
最初は家族だけの静かな環境で過ごし、徐々に日常生活に適応させることが大切だという。
阪神・淡路大震災をはじめとした被災者の心のケアの経験が豊富な
加藤寛・兵庫県こころのケアセンター副センター長は、
「カウンセリングなどのサポートが最も必要になるのは、救出された人たちが、
再び鉱山の仕事に戻る時。恐怖で鉱山に入れない人が多く出てくるかもしれず、
継続的な支援が重要だ」と話す。
皮膚炎、肺炎にも要注意。
地下は閉鎖空間という点で、国際宇宙ステーションと共通している。
宇宙航空研究開発機構で宇宙医学を研究する大島博主幹研究員は
「暗い閉鎖空間に2か月以上いたことで、体内リズムが乱れている可能性がある。
不眠や集中力低下のほか、長い期間リズムが乱れると心血管疾患を起こす恐れもある」と指摘。
回復させるには救出後も規則正しい生活が欠かせないという。
暗い場所に居続けたため、目の瞳孔も常に散大した状態になっている。
大島さんは「そのままで日光を浴びると視神経を痛める危険性がある。
救出時はサングラスを着用し、その後も暗めの部屋で目を慣らし、
少しずつ明るい場所に移るべきだろう」と話す。
人によっては、高温多湿の環境のために多量の発汗で皮膚炎が起きたり、
粉じんを吸い込んで気管支炎や肺炎を発症したりすることも懸念材料。
大島さんは「個々人を観察しながら、少しずつ適応させる必要がある」とアドバイスする。
(記事提供:読売新聞)
これから、経験した彼らにしかわからない辛い現実が待っています

しっかりしたサポートも必要ですが、彼ら自身が治れるかどうかだと思います。
命ある限り明るく楽しいことがあるのも事実

現実を受け入れ、焦らず前向きに乗り越えてほしいと祈ります

(以下読売新聞より。)
チリの鉱山落盤事故で、過酷な閉鎖空間に2か月以上閉じこめられていた33人。
救出された作業員たちは元気そうに救助隊員らと抱擁したが、
心身にさまざまな異常が起きることが懸念されるため、
専門家は中長期を見すえた治療とケアの必要性を強調している。
作業員の健康問題で、今後も手当てが必要なのが「心の傷」だ。
恐怖場面が繰り返しよみがえるフラッシュバックや不眠が生じるPTSD(心的外傷後ストレス障害)、
うつ病などを発病する恐れがあるからだ。
防衛医大防衛医学研究センターの高橋祥友教授(精神医学)は
「突然に長期間、隔絶された空間で死の危険にさらされた作業員たちの受けたストレス
は計り知れない。アルコールや薬物依存に陥る可能性もある」と話す。
高橋教授によると、少なくとも1年間は、心身の健康を定期的にチェックする必要があり、
最初は家族だけの静かな環境で過ごし、徐々に日常生活に適応させることが大切だという。
阪神・淡路大震災をはじめとした被災者の心のケアの経験が豊富な
加藤寛・兵庫県こころのケアセンター副センター長は、
「カウンセリングなどのサポートが最も必要になるのは、救出された人たちが、
再び鉱山の仕事に戻る時。恐怖で鉱山に入れない人が多く出てくるかもしれず、
継続的な支援が重要だ」と話す。
皮膚炎、肺炎にも要注意。
地下は閉鎖空間という点で、国際宇宙ステーションと共通している。
宇宙航空研究開発機構で宇宙医学を研究する大島博主幹研究員は
「暗い閉鎖空間に2か月以上いたことで、体内リズムが乱れている可能性がある。
不眠や集中力低下のほか、長い期間リズムが乱れると心血管疾患を起こす恐れもある」と指摘。
回復させるには救出後も規則正しい生活が欠かせないという。
暗い場所に居続けたため、目の瞳孔も常に散大した状態になっている。
大島さんは「そのままで日光を浴びると視神経を痛める危険性がある。
救出時はサングラスを着用し、その後も暗めの部屋で目を慣らし、
少しずつ明るい場所に移るべきだろう」と話す。
人によっては、高温多湿の環境のために多量の発汗で皮膚炎が起きたり、
粉じんを吸い込んで気管支炎や肺炎を発症したりすることも懸念材料。
大島さんは「個々人を観察しながら、少しずつ適応させる必要がある」とアドバイスする。
(記事提供:読売新聞)
Posted by 望月 伸洋 at 08:31│Comments(0)
│メンタル